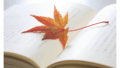「招き猫」の片手を挙げた愛らしい姿は特徴的で、日本ではお店などに置かれているため、誰もが一度は目にしたことがあり、外国人観光客のおみやげとしても多く見かける、身近なものではないでしょうか。
広く知られた招き猫ですが、福を呼ぶ縁起物となった由来の諸説や、左手・右手・両手と挙げるポーズや色による意味の違いなど、探ってみると興味深いものがありました。どうぞご覧ください。
招き猫の由来諸説

招き猫の発祥とされる寺社や由来は諸説存在します。中でも特に有名なものをご紹介します。
穀物を守る存在として
古来より猫は、ネズミなどを駆除し穀物を守る役割から、家庭や商店に住み着くと商売が繁盛するとされ、福を呼ぶ動物と見なされてきました。
現在とは異なり、猫が少なかった江戸時代には、猫の絵を描いた紙を店に貼ることで、猫がいるかのように見せて縁起を担いだことが、招き猫の起源とも言われています。
豪徳寺の由来説
東京都世田谷区にある「豪徳寺(ごうとくじ)」は、猫寺とも呼ばれています。
江戸時代、近江彦根藩の藩主であった井伊直孝は、この地で鷹狩りの途中、荒れた寺の前で手招きする白猫に誘われて寺を訪れました。
和尚による説法中に突然の雷雨がありましたが、雨宿りができただけでなく、有意義な話を聞くことができたため、直孝は深く帰依し寺の修復に寄進を行いました。
これが縁で、豪徳寺は井伊家の菩提寺となるとともに、その猫は「招福猫児(まねぎねこ)」として祀られ、「招福殿」も建立されました。
その後、白猫が手招きする姿を模した「招福猫児」が、陶器で作られるようになり、現在でも奉納されており、多くの願い事が叶う場所として知られています。
自性院の由来説
「自性院(じしょういん)」は東京都新宿区にある寺院で、室町時代に活躍した武将、太田道灌(おおたどうかん)に関連する逸話があります。
江古田原・沼袋の戦い(えこたはら・ぬまぶくろのたたかい)で劣勢に立たされていた道灌が、逃走中に道に迷った際、突如現れた手招きする猫に導かれ自性院に辿り着き、危機を脱しました。
この出来事が転機となり、形勢を逆転した後、感謝の意を込めて猫地蔵を奉納し、その地蔵が招き猫の元の元となったとされています。
江戸時代には豪商による猫地蔵の奉納もあったということです。
今戸神社の由来説
江戸時代、浅草に住む貧しい老婆が経済的な理由で飼い猫を手放してしまったある夜、夢にその猫が現れ「自分を模した人形を作れば福徳が得られる」と告げました。
この助言に従い、猫の形をした陶磁器の人形を今戸焼(いまどやき)で制作し、浅草寺(せんそうじ)近くで販売したところ、すぐに評判ととなりました。
(今戸神社が今戸焼発祥の地との石碑がありますが、招き猫との関連は定かではないようです。)
これらの人形は「丸〆猫(まるしめのねこ)」と呼ばれ、福徳や財をもたらす象徴とされています。特徴は、身体の後ろに〇の中に〆が描かれたマークがあり、顔は正面、身体は横を向いていて、お地蔵様のようによだれかけを身に着けています。
栴壇王院無常法林寺の特別な招き猫
「栴壇王院無常法林寺(せんだんのういん むじょうほうりんじ)」は京都府京都市にある寺院で、「主夜神(しゅやじん)」と呼ばれる夜を守る神様が祀られています。
黒猫はこの神様の使者とされており、江戸時代には、主夜神尊の銘を刻み右手を挙げる黒色の招福猫が作られ、参拝者に授けられていたそうです。
その他にも
その他の寺社が複数、民間信仰や伝承など、日本各地にさまざまな発祥の説があり、伝統工芸品や民芸品と共に広まっていったとされています。
(一例として、猫をかわいがっていた魚屋の主人が、ある日病に伏して働くことが出来なくなってしまったところ、飼い猫が小判を持って帰ってきて主を救ったという話など。)
手の位置と色に込められた意味

左手を挙げる意味
左手を挙げた招き猫は一般に「千客万来(せんきゃくばんらい)」を象徴し、人徳によって多くの来客を招き、良縁を呼び寄せるとされました。
江戸時代には、民間で左手を挙げる招き猫が一般的であったと言われています。
右手を挙げる意味
右手を挙げる招き猫は「金運招来(きんうんしょうらい)」を象徴し、特に金運や幸運といった福徳をもたらすとされました。
寺社から授かるのは、この右手を挙げたデザインが多く見られます。
また近年一般的に多くの招き猫が右手を挙げているのは、一説には右利きが多いことや、右手でお金を受け取る習慣が影響しているともいわれています。
両手を挙げる現代的解釈
従来、招き猫は左手または右手のどちらか一方を挙げるものでしたが、最近では両手を挙げるデザインも登場しています。
これは「千客万来」と「金運招来」の両方を兼ね備えた意味が込められているためですが、このスタイルは「お手上げの万歳」や「欲張りすぎ」と見なされ、好まれないこともあるようです。
手の高さによる意味
手を挙げる高さにも意味があるそうで、「手長(てなが)」とは耳より上に手を挙げるものとして、高いほど遠くから大きな福を呼び寄せると言われます。
一方、「手短(てみじか)」とは耳より下に手を挙げるもので、身近な幸運を招いてくれるとされています。
色による意味の例

さまざまな解釈がありますが、一例として挙げていきます。
ご自身のラッキーカラーを選んでも、良いようです。
白:開運招福、商売繁盛
黒:魔除け、厄除け
赤:病除け、無病息災
金色、黄色:金運上昇、良縁
ピンク:恋愛成就
青:学業成就
緑:家内安全、交通安全
紫:長寿
置き場所や手放し方

適した置き場所は
伝統的には、神棚の下に「縁起棚(えんぎだな)」を設置して、他の吉兆をもたらす物と一緒に飾られてきました。
現在は神棚もなく縁起棚を設置するのが難しい場合も多いため、お店では、人の目に触れやすいレジ横など目立つ場所に置いています。
ご自宅では、玄関や人の出入りが多い部屋やリビングのタンスの上など、少し高めの目につきやすい位置にスペースを作って置くとよいでしょう。
招き猫は、陶器や木彫りに始まり、張り子や木目込み、プラスチック製など様々な素材で作られるとともに、ぬいぐるみやシール、キーホルダー、キャラクターとのコラボ商品など、多様な展開で親しまれています。
破損に留意しながら、愛着を持って扱えるとよさそうですね。
手放す時は
破損したり、転居や店舗再開などで新しい招き猫をお迎えし、これまでのものを手放す場合は、お焚き上げしていただける寺社に奉納できるとよいですよね。
そのようなところが近くにないなど難しい場合には、これまでの感謝を伝え、お清めの塩をしたあと、目の部分を白い紙などで隠してから、袋に入れるなどして、自治体の規定に従って、燃やさないゴミの日などに出します。
地域に息づく伝統工芸と招き猫のつながり

三大産地
招き猫は、各地の伝統的な焼き物や民芸と融合し、地域文化を象徴する存在としても親しまれています。
なかでも日本三大産地として知られるのが、次の三つです。
・愛知県・常滑焼(とこなめやき):赤土の素地を活かした素朴な風合いで、全国シェアの多くを占めています。代表的な白猫の招き猫「とこにゃん」は、常滑市のシンボルとしても有名です。
・愛知県・瀬戸焼(せとやき):滑らかな質感と鮮やかな色合いが特徴で、今戸焼の流れを継ぐとも言われています。細やかな絵付けが施された華やかな招き猫も多く見られます。
・石川県・九谷焼(くたにやき):豪華な色絵と金彩が魅力で、芸術品としての価値が高いのが特徴です。飾って楽しむインテリアとしても人気があります。
近年では、ガラス製・和紙製・木目込み細工・キーホルダー・ぬいぐるみなど、伝統と現代感覚を融合させた多彩な招き猫も登場しています。
地域ごとの素材や色づかいに宿る個性を通して、日本文化の奥深さを感じられるのも、招き猫の魅力といえるでしょう。
招き猫の日やおまつり
1995年に日本招猫倶楽部によって、招き猫に感謝を表す記念日として、毎年9月29日は「招き猫の日」と制定されたそうです。
日づけの由来は、福を招くことから「来る(9)ふ(2)く(9)」の語呂合わせによるもので、この時期になると、三重県伊勢市のおかげ横丁や愛知県瀬戸市では、「来る福招き猫まつり」が開催されています。
まとめ

猫は、古来より穀物や家・商売を守り福を招く動物とされてきました。
その後も、難を逃れご利益や福を呼び寄せた諸説の由来などから「招き猫」が作られ、各地の工芸品などによって、縁起物として広く認知されています。
・左手を挙げた招き猫は、人々や客を引き寄せる「仁徳や良縁」「千客万来」
・右手を挙げた招き猫は、主に経済的な豊かさを招く「福徳」「金運招来」
さまざまな色の招き猫や、置物以外の形態としてぬいぐるみやキーホルダー、シールなども登場しています。
かつては縁起棚という特定の場所に置かれていましたが、現在は多様な願いを込めて、様々な場所で愛されているといえるでしょう。
また、日本各地の伝統工芸と融合した招き猫は、地域の魅力を伝える文化的な存在としても受け継がれています。
通年ご縁のあるものではありますが、機会がありましたら、9月29日招き猫の日やおまつりも意識してみると、また特別な体験ができるのではないでしょうか。