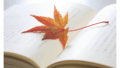急な降り出しやレインコート程ではない雨の日、傘を差していても、気づけば肩や足元、リュックが濡れてしまい「どうにかならないかな」と思いませんか?
実は、傘のサイズや角度、歩き方を少し工夫するだけで、濡れにくさはぐっと変わります。
今回は、すぐに役立つ傘の差し方・歩き方・公共の場でのマナー、さらに傘の歴史もご紹介し、日常に役立つ実用的なヒントと豆知識をお届いたします。
雨に濡れにくい傘の差し方

傘の大きさと選び方
傘で雨を防ぐには、まずサイズ選びが重要です。傘を広げたときの直径を「差し渡し」と呼びますが、これが小さいと体の一部や荷物が雨にさらされてしまいます。
目安として
- 身長155cm前後なら91~96cm
- 160cm前後なら94~99cm
- 170cm前後なら100~105cm
- 175cm前後なら108~113cm程度 の差し渡しを選ぶとよいでしょう。
荷物が多い日には、ひと回り大きめサイズを持っておくと余裕が生まれます。
傘を持つ高さと角度

傘は持ち方ひとつで濡れ方が大きく変わります。
頭が半分隠れるくらいまで傘を下げ、肩や脇のあたりに中棒を軽く当てると、腕の負担も少なく安定します。
また、進行方向に対しては15度ほど前に傾けると、足元までカバーしやすくなります。風が強い日は、風上に少し傾けると雨を受け流しやすいです。
顔を覆いすぎると前が見えにくく危険なので、視界の確保も忘れないようにしましょう。
荷物が濡れにくい傘の差し方
買い物袋やハンドバッグを持っていると、どうしても外側が濡れてしまいがちです。
はっ水機能付きのバッグやレインバッグカバーを用いるとともに、急な雨や長時間の外出時には困りますよね・・・。
その対策として有効なのが「クロスする持ち方」で、たとえば右手に傘を持っている場合は、左肩の方に斜めに構え、体と傘を交差させるように持つ方法です。
荷物を体側に寄せて覆うことができ、ある程度守ることができますよ。
リュックが濡れにくい傘の差し方とカバーの利用
リュックは背中に背負うため、普通に傘を差すと外にはみ出しやすいのが難点ですよね。
濡れにくくするには、
- リュックを前に抱える
- 傘を背中寄りに傾ける
- 防水スプレーと専用のリュックカバーを活用する といった方法があります。
最近は、背中側まで覆える大型傘や二股タイプも登場しているので、雨の多い地域では検討する価値もあります。
雨の日に足元が濡れにくい歩き方

靴選びと防水対策
雨の日に泥はねなどを避け、気持ちよく過ごすためには足元の備えも欠かせません。
レインシューズや防水加工されたスニーカーはもちろん、レインシューズカバー・防水スプレーや撥水加工の靴下を活用すると役立ちます。
日頃から準備しておくと、急な雨でも不快感を最小限に抑えられるでしょう。
歩き方のポイント
歩き方を少し変えるだけでも、足元の濡れ方は大きく違います。
- 歩幅はやや狭めに(普段の6〜7割程度)
- 足裏全体でやさしく着地(パンプスの場合は、土踏まずあたりからそっと地面に置くような感覚で歩くと、靴への衝撃や水はねを軽減できます)
- 背筋を伸ばし姿勢をまっすぐに保つ
こうすることで泥はねが起きにくくなり、靴や裾の汚れを軽減できます。大股歩きやがに股歩きは、かえって水しぶきを浴びやすいので避けたいところです。
公共の場での傘マナー

開閉時の注意
傘を開くときは、必ず先端の石突(いしづき)を下に向けた状態で開きましょう。持ち上げながら広げると周囲に水滴が飛び散りやすく、人に当たる危険もあります。
閉じるときも石突を地面につけたまま静かにまとめ、水滴は軽くしごく程度にとどめます。大きく振り払うと周囲にかかってしまうので避けましょう。
傘袋がある場合は、その場で素早く収納するとスマートです。
閉じた和傘・折り畳み傘の持ち方

閉じた傘を手に持つときは、先端を下に向け、体に沿わせて持つのが基本です。
混雑時は前後に振らないよう注意し、エスカレーターや階段では片手で体側にぴったりと添えるとよいでしょう。
折り畳み傘はカバーに入れておくと、周囲を濡らさず自分の荷物も清潔に保てます。
歩道や人混みでの持ち方
狭い歩道や人通りの多い道では、傘を大きく傾けすぎないことが大切です。
すれ違う相手の頭に当たらないよう、少し持ち上げるなど柔軟に対応しましょう。肩幅を意識して傘を中心に保つと、周囲とぶつかりにくくなります。
電車・バス内での傘の扱い

濡れた傘は、必ず留め具でまとめ、可能なら傘袋に入れます。
立っているときは足元に垂直に立てかけ、先端を通路に出さないよう注意します。
網棚に直接置くと水滴が落ちてしまうため避けること、必要ならタオルで軽く拭いてから傘袋などに収納することも、周囲への配慮になります。
車・タクシー利用時の配慮
タクシーや車に乗る前には、傘の水滴を軽くしごき落としてから畳みます。
車内では座席やマットを濡らさないよう、閉じた傘を体の側面に抱え込むように持つとよいでしょう。タオルや小さなビニール袋を常備しておけば、さらに快適に利用できます。
傘立ての使い方
公共施設や店舗の傘立てを利用するときは、他人の傘と取り違えないよう、留め具や名札を付けておくと間違い防止になります。
最近は鍵付きタイプや傘専用袋が用意されている施設も増えているので、利用前に確認すると良いでしょう。
濡れたままの傘を床に置くと滑りやすく危険なので、必ず傘立てや指定の袋に収めるようにしましょう。
傘の歴史をたどる 〜差し掛け傘から折り畳み傘・ビニール傘まで〜

古代の傘は「地位の象徴」
傘の歴史をさかのぼると、その起源はおよそ4000年前の古代エジプトやペルシャにまでたどり着きます。
壁画には、王や貴族が日差しを避けるために傘を掲げる姿が残されており、当初の傘は「雨具」ではなく、権威や地位を象徴する日傘としての意味合いが強かったと考えられています。
日本に伝わった「差し掛け傘」から和傘

日本でも古墳時代に大陸から伝わった当初は、天蓋のように頭上に差し掛ける「差し掛け傘」が主流でした。
これは宗教儀式や貴人の外出に用いられ、従者が主人の頭上に掲げる形式で、まさに地位の象徴とされていたのです。
その後、竹と和紙を用いた和傘として独自の発展を遂げ、江戸時代には庶民にも普及し、祭礼や芝居の小道具としても広く使われました。
雨傘を広めたイギリス人
現在の「雨傘」としての普及はヨーロッパから始まります。
18世紀後半、イギリスの旅行家ジョナス・ハンウェーが、防水加工した傘を雨の日に差して歩いたのがきっかけでした。
当時は男性が傘を持つ習慣はなく、彼は「変わり者」と冷やかされましたが、30年にわたり傘を使い続けたことで、次第にロンドンの街に雨傘文化が定着していったのです。
その後、基本的な形状は200年以上経った今でも変わらないそうですよ。
折り畳み傘の誕生
さらに20世紀になると、傘の歴史を大きく変える発明が登場します。
1928年、ドイツの技術者ハンス・ハウプトが世界初の折り畳み傘を考案しました。彼は「片手でも持ち運びやすい傘を作りたい」という強い思いを抱いていました。当時の傘は長く、電車や建物に持ち込むと不便で置き忘れも多かったそうです。
そこで彼は、短く折り畳んでポケットやバッグに収められる仕組みを工夫し、特許を取得します。誕生した折り畳み傘は「Knirps(クニルプス)」と名付けられ、やがてドイツ語で「折り畳み傘」を意味するほど定着。
戦後は日本でも改良が進み、三段折りや軽量化が普及し、現代の通勤・通学に欠かせない存在となりました。
日本発の「ビニール傘」

日本発の革新もあります、それが「ビニール傘」です。
東京浅草の老舗メーカー・ホワイトローズが1958年に試作したのが最初とされ、当初は乳白色で視界が悪く、売れ行きは芳しくありませんでした。
しかし1964年の東京オリンピックを契機に透明タイプが注目され、街中でも周囲が見やすい傘として一気に普及しました。
大量生産でき安価な点も相まって、現在では日本国内で年間1億本以上が消費されるほどの国民的アイテムとなりました。
傘の歴史変遷が映すもの
こうしてみると、傘は単なる雨具にとどまらず、人々の暮らしや時代背景を映し出す存在ともいえるのではないでしょうか。
古代の「差し掛け傘」に始まり、和傘、折り畳み傘、ビニール傘へ──その変遷を知ることで、雨の日が少し楽しく、奥行きのある時間に感じられるかもしれませんね。
まとめ

雨の日は、ちょっとした工夫が大きな差を生みます。傘の選び方や持ち方、歩き方ひとつで濡れにくさも変わり、さらに公共の場でのマナーを意識することで、自分も周囲も心地よく過ごせますね。
- 傘はサイズ・高さ・角度を意識することで濡れにくさがアップ
体格に合った大きさを選び、15°程度前傾の角度で差すだけで雨の当たり方が大きく変わります - 荷物やリュックを守るには持ち方の工夫と補助アイテムが効果的
クロス持ちやカバーの利用で、大切な荷物を雨からしっかり守ることができます - 足元は歩幅を狭め、ソフトな着地で泥はねを防げる
レインシューズのほか、歩き方を少し変えるだけで、靴や裾の汚れをぐっと減らせます - 公共の場では開閉・持ち方・傘立ての利用など周囲への配慮を
傘は思いのほか場所を取る道具だからこそ、石突を下にした開閉などのマナーを意識しましょう - 歴史を知ると、傘は単なる雨具ではなく文化を映す存在であることがわかる
差し掛け傘から現代の折り畳み傘まで、傘の歴史変遷は人々の暮らしや価値観を映し出してきたのですね
このほかにも、ご自身なりの服や足元が濡れにくい方法を研究している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自分もその一人として、今後も検索してアイデアを探していきたいと思っております。
雨の日も煩わしさから解放され、むしろ新しい発見を楽しめる時間に変わるきっかけになりましたらさいわいです。