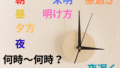秋の行楽シーズン、全国各地の紅葉の名所を訪ねるのも楽しみの一つ、という方も多いのではないでしょうか。
この時「紅葉狩り(もみじがり)」と呼ばれる言葉の意味や由来は何かを知ると、いっそう趣深く楽しめるかもしれません。
季節を楽しむお供に、木々が紅葉する理由とともに併せてご覧ください。
紅葉狩りとはどんな活動?

秋はレジャーに最適な季節で、日本の秋を代表する行楽の一つが「紅葉狩り(もみじがり)」です。
いったい何を狩るのか?と思いそうですが、紅葉狩りは何をするかというと、「山や野の美しく色づいた紅葉を眺めに出かけること」です。紅葉を鑑賞し、楽しむこと全般といえます。
紅葉を狩るというと、もみじなど紅葉した木の枝や葉を実際に摘んで持ち帰り何かに使うのかと、勘違いしてしまいそうです。
実際、幼少期には落ち葉を拾って持ち帰ったこともありましたし、木の枝を折らないよう注意書きされた看板を目にしたこともあり、疑問に思っていたこともありました。このような誤解も、今となっては紅葉狩りとは何をするものなのか、知る前の面白い逸話です。
紅葉狩りの由来は

紅葉狩りは、もともと平安時代の宮廷や貴族社会に端を発し、やがて庶民の行楽へと広がった日本の秋の文化的行事です。
「狩り」というと、「hunting」のような野山に入り獣や鳥を捕えることを指します。
なぜ「紅葉狩り」に「狩り」の言葉が用いられているのでしょうか?
「狩り」の由来や意味の変遷
「狩り」や「狩る」という言葉は元々、野山での狩猟を意味しており、「鹿狩り」や「鷹狩り」などがありました。
さらに時代を経るにつれて、薬草などの植物や果物の採取、山菜やきのこきのこ採りのために、山に入って探す行為を狩猟になぞらえて「~狩り」という言葉が広がり、「薬狩り」「きのこ狩り」「梨狩り」「ぶどう狩り」「いちご狩り」など、さらには魚や貝の採取である「しじみ狩り」などと、広範な採集行動を指すようになりました。
現在ではこれらの行為は、果樹園や観光地での観光体験などとしても知られるようになりましたが、元は自然の中で直接植物や果物を収穫する行為が始まりと言われています。
桜狩りとの関連から
「紅葉狩り」よりも古い時代の『宇津保物語』や『古今和歌集』に「桜狩り」という言葉が、春に使われていました。
桜狩りや紅葉狩りは、もともと「草花を愛でその美しさを求めて出かける」行為として実際に野山に入り、木の枝を手折って持ち帰る習慣があったとされ、そうした行為に由来するともいわれています。
特に貴族や公家の女性など、外出が制限されていた人々のために、彼らが直接自然を楽しむ代わりに、桜や紅葉の枝を採って贈るという風習がありました。
これらの背景から、狩猟をしない貴族が草花を愛でることを「狩る」と表現するとした説や、紅葉を手に取る行為を「狩る」と考える説などがあります。
和歌の題材として
『万葉集』では、主に萩(黄葉)や楓(紅葉)など季節の色づく葉を愛でる歌が詠まれており、特に奈良時代は黄色い「黄葉」が主流でした。その後、赤い「紅葉」への関心も高まり、『古今和歌集』時代には紅葉を秋の象徴とする歌が増えていきます。
その流れを汲んで平安時代の宮廷においても、紅葉狩りは「紅葉見(もみじみ)」として貴族同士の交流や宴、和歌の題材として親しまれていました。
例えば嵯峨野や小倉山など紅葉の名所に分け入って、美しい景色を鑑賞しながら和歌を詠みあうといった催しなどから、『百人一首』では宇多上皇のこころを詠んだ歌が有名ですね。
「小倉山峰の紅葉ば心あらば今ひとたびのみゆき待たなん」貞信公(藤原忠平)「百人一首」26番
意訳:小倉山の峰の美しい紅葉の葉よ、お前に人の情がわかる心があるなら、もう一度(醍醐)天皇がおいでになるまで、散るのを急がないで待っていてほしい。
さらにのちの時代になると「紅葉狩り」という言葉も定着し、江戸時代に入ると、街道や観光地の整備、行楽地としての仕掛けが進み、庶民層にも浸透し、秋の代表的な行楽となりました。
こうした古典文学に見る紅葉鑑賞や桜狩りの場面は、時代を超えて受け継がれ、現代の私たちにも四季と深く向き合う心の豊かさを伝えてくれるものといえましょう。
鬼女紅葉(きじょもみじ)の伝承
紅葉狩りにまつわる伝承の中でも特に有名で魅力的なのが、長野県に伝わる「鬼女紅葉(きじょもみじ)」の物語で、平安時代を舞台とし「紅葉狩り」の由来の一つともいわれています。
鬼女紅葉伝説 ― 美しくも恐ろしい鬼女の物語
今から約千年前、奥州会津の笹丸・菊世という夫婦が子授かりの祈願をしたところ願いが叶い、一人の美しい娘「呉葉(くれは)」が生まれます。
成長した呉葉は都へ上り、名を「紅葉(もみじ)」と改め、源経基(みなもとのつねもと)という武将の側室となり寵愛を受けました。
しかし、源経基の正妻が病に倒れると「紅葉が呪いをかけている」と疑われ、都を追われて信濃の戸隠山(とがくしやま)や鬼無里(きなさ)の山奥へ流されてしまいます。
村人たちはその美しい紅葉を敬愛し、都を偲んだ地名を付けるなど大切にしましたが、やがて彼女は都に戻る望みを募らせ、夜になると妖術を用いて近隣の村々を荒らす鬼女となってしまいました。
噂は都まで伝わり、帝は武将・平維茂(たいらのこれもち)に紅葉退治の命を下します。
維茂は初めての戦いでは妖術に敗れますが、北向観音(きたむきかんのん)に祈願し「降魔(ごうま)の剣」を授かって戦いに臨みます。
激しい戦いの末、紅葉はこの剣によって討伐されてしまいました。
この物語は、室町時代から能や浄瑠璃、歌舞伎の題材として盛んに演じられ、特に歌舞伎の演目『紅葉狩』として有名です。
伝説の舞台となった戸隠には紅葉の菩提を弔う寺院も存在し、今も地域の文化や祭りにも深く根付いています。
この伝説は、単なる自然観賞を超えて、古くから日本の自然と人の心が交錯する物語性を持つことを示し、紅葉の美しさの裏に潜む幻想や畏怖が、季節と風景にさらに深い意味を与えているといえるのではないでしょうか。
紅葉狩りの多彩な楽しみ方

紅葉狩りは、はじめに平安時代に貴族間で広まりました。
当時は、紅葉を観賞しながら宴会を行い、紅葉の景色を和歌に詠む「紅葉合(もみじあわせ)」という遊びが流行しました。
江戸時代に入ると、この風習は庶民にも広がり、紅葉狩りが秋の定番行事として根付いていきました。
紅葉するメカニズム
紅葉(こうよう)は、主にイチョウやモミジのような落葉樹で観察されます。
秋に気温が下がると、これらの樹木は冬に備えて葉を落とすため、葉への栄養分の供給を停止します。
このプロセスにより、葉の葉緑素が分解され始めます。
葉緑素がなくなると、通常は見えない赤や黄色の色素が顕在化します。
例えば、黄色いイチョウの黄葉や、赤いカエデの紅葉があります(どちらも「こうよう」と読みます)。
樹種によって異なる色の出方は、それぞれの樹木が持つ栄養素の違いによるものです。
これにより、秋の美しい景観が生まれますが、紅葉は、樹木が冬を迎える準備の一環なのです。
春にも出会える「春紅葉(はるもみじ)」とは
春先の青もみじに混ざって、赤く色づいたもみじに出会ったことはありませんか?
こちらは「春紅葉(はるもみじ)」と呼ばれる現象です。
春先の新芽は葉緑素がまだ少なく、もともと含まれているアントシアニンなどの色素によって赤や橙色に色づくことがあります。
日差しの強さや寒暖差にも影響され、日当たりが良く気温差の大きい場所ほど鮮やかな春紅葉が見られやすい傾向にあるといわれています。
特にイロハモミジやベニシダレなどの品種でよく見られ、土壌や木の健康状態によっても色合いが違ってくるのが特徴です。
この春紅葉も、季節の移ろいを感じる自然の彩りのひとつといえるでしょう。意外とご近所で見つけることもできますので、よろしければ探してみてくださいね。
多彩な方法で楽しめる
日本の紅葉は、その美しさで特に知られています。
日本の大部分が森林で覆われており、多様な落葉樹が存在するためであり、また、寒暖の差が激しい気候であるため、これらの環境が紅葉の色づきを促すといわれています。
日本の各地で美しい紅葉を見ることができるのは、この国特有の気候と関連しているのですね。
そのため、紅葉狩りはその人それぞれに合った方法で、見る人によって異なる楽しみ方があります。
近場で手軽に楽しむこともできます。通勤で通る街路樹、地元の公園や神社などの散策で、落葉を楽しんだり、美しい落ち葉を集めたりすることも一つの方法です。
紅葉を眺めることができるカフェでお茶をしながら過ごすのも素敵ですし、ドライブで色とりどりの景色を楽しむのも良いでしょう。
さらには遠出して山々を眺めたり温泉からの景色に安らいだり、キャンプや秋の味覚をいただく旅行先や観光地も、少し歩けば容易に秋の風景を見つけることができます。
日本全国どこでも、この時期ならではの季節の贈り物として楽しめるのが、醍醐味といえましょう。
その際は当然のことではありますが、公園や観光地によっては落葉や枝の採取が禁止されている場合や、写真撮影・飲食に関しても周囲への配慮を忘れずに、現地のルールやマナーを守って、長くこの文化を楽しみ継承していけるよう、各自が意識して過ごすようにしたいものですね。
まとめ

「紅葉狩り」という行為は、紅葉の美しさを鑑賞して楽しむことにほかなりません。
かつての狩猟になぞらえて、山に入って草木や植物などを探す行為を「~狩り」という言葉で表しています。
この行事は、晩秋のみに体験できる特別なものです。
季節の変わり目を感じさせるその美しさと移ろい、そして落葉することで、次の春に向けた樹木の準備が進むメカニズムは、大いなる自然の力の現れに触れる機会ともいえるでしょう。
そして、美しさの裏に潜む幻想や畏怖の念とともに、日本の自然と人の心が交錯する物語性や深い意味を与えてくれるような、自然鑑賞を越えた何かに没入することもできるかもしれません。
日常の一コマでも体験できる紅葉狩りで、一息ほっこりされますように。