「秋の七草」と聞いてすぐに答えられる人は、俳句や歌に通じた風流な人かもしれませんが、どことなく耳にすると、多くの人が日本らしい秋の風情を感じるのではないでしょうか。
七種類の植物とは何か、春と秋との違い、いつからどう選ばれたものといわれているのか、などについて調べてみました。
せっかくですのでお子さんと一緒に覚えておくと、ちょっと豊かな気持ちになれそうです。
秋の七草の意味

秋の代表の草花
「秋の七草」とは、古くから親しまれている秋の代表的な草花を指します。
冬の訪れを前にして、その美しさを楽しみつつ、薬効も期待される植物が選ばれているとともに、時代を超えて日本人の生活や文化、風習の中で大切にされてきました。
時代によって少々変遷はありますが、今日では次の植物が「秋の七草」と認識されています。
「ハギ、オバナ(ススキ)、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、アサガオ(キキョウ)」
由来とされるものは
秋の七草を選定したのは誰なのかは明確にはされていませんが、奈良時代の歌人、山上憶良が万葉集で詠んだ歌が由来ではないかと言われています。
・「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花」(万葉集・巻八 1537)
・「萩の花 尾花(をばな) 葛花(くずはな) 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし) また藤袴(ふぢはかま) 朝貌(あさがほ)の花」(万葉集・巻八 1538)
なお、「朝貌(あさがほ)」に関しては諸説ありますが、現代では「桔梗」として広く認識されています。
秋の七草の種類
ハギ、オバナ(ススキ)、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、アサガオ(キキョウ)について、花の写真と共にみていきます。
萩(ハギ)

マメ科、開花は7~10月頃、山や川辺、海岸近くなど水はけのよいところで生育。
「草冠に秋」という字の如く、秋の象徴的な野花で、紅紫の小さな蝶形の美しい花を咲かせます。
秋のお彼岸の際に食べられる「おはぎ」はこの花にちなんで名付けられたとも言われています。
尾花(オバナ)

イネ科、開花は7月~11月頃、乾燥した山地や野原で自生。
尾花はススキの別称で、穂が動物のしっぽに似ていることから名づけられ、穂の部分が花であることが特徴です。
桔梗(キキョウ)

キキョウ科多年草、開花は6月~10月頃、山や平地の日当たりの良い場所で生育。
鮮やかな青紫色の五角形の花を持ち、武士たちにも愛され家紋などにもみられます。
撫子(ナデシコ)

ナデシコ科多年草、開花は4月~11月頃、山や河原などで多く自生。
柔らかなピンクや白色の花が特徴的で、「やまとなでしこ」とも呼ばれ親しまれています。
万葉集にも詠まれるなど、古くからの愛される花です。
葛(クズ)

マメ科蔓性の多年草、開花は8月末~9月中旬頃、山や森の中、藪などでひと夏に10メートル位まで繁茂。
白や紫の花を咲かせたあと、結実してエダマメのような実を付けます。
根からは「葛粉(くずこ)」として知られるデンプンを取ります。また、漢方の「葛根湯」の原料としても使われています。
藤袴(フジバカマ)

キク科多年草、開花は8月~10月頃、湿地や水辺の近くの土手などで生育。
白やピンク、藤色で袴のような形の花びらの小花が密集して咲く形が特徴で、桜餅のような良い香りがするため平安時代には髪を洗ったり芳香剤として利用された香草です。
女郎花(オミナエシ)

オミナエシ科、開花は6月~10月頃、日当たりの良い草地や道端、林の下草などで生育。
小さな黄色い五弁の花が密集して咲きます。「おみなえし」の名は、「美しく力強い女性」を意味する言葉から来ています。
また、粟(あわ)の花に似ているため女飯(おんなめし)」の名に由来するとも言われています。根や草を乾燥させて煎じたものは生薬として。
春の七草との違い

主な違いは2つあります。
- 草花の種類の違い
- 文化的な違い
草花の種類の違い
春の七草は、「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ」で、秋の七草とは全く異なります。
「スズナ」はカブ、「スズシロ」は大根の別名で、「ナズナ」は「ぺんぺん草」としても知られていますが、秋の七草には別名で親しまれている植物は少ないようです。
文化的な違い
春の七草は食用の植物が中心で、1月7日に「七草粥」として食べる風習があります。
一年の無病息災を願うという意味が込められています。
これに対して、秋の七草は観賞用の植物が中心で、食べる文化はありません。
お月見の際に飾られたり、季節の変化を感じ取る観賞や詩や歌に詠まれることを目的として楽しまれています。
秋の七草を覚える方法
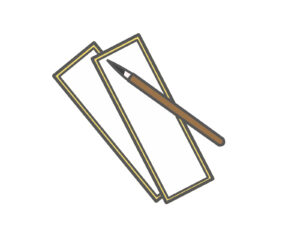
「5・7・5・7・7」のリズムで
秋の七草を覚えるには、古の歌を利用するのが効果的です。
春の七草は、「5・7・5・7・7」のリズムに合わせて
「せりなずな、 ごぎょうはこべらほとけのざ、 すずなすずしろ、 これぞ春の七草」と覚えませんでしたか?
こちらの作者は、室町時代に源氏物語の注釈書の 「河海抄 (かかいしょう)」を著した 四辻善成(よつつじ よしなり) 、もしくは同じく室町時代の連歌の注解書「梵灯庵袖下集(ぼんとうあんそでしたしゅう)」を記した連歌師(れんがし)の梵灯(ぼんとう)などと言われています。
同様に、先に挙げた山上憶良(やまのうえのおくら)による万葉集の歌に、秋の七草がすべて含まれていますので、こちらを活かします。
ただし、「朝顔」は当時は桔梗を指していたため注意が必要です。
・「萩の花 尾花(をばな) 葛花(くずはな) 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし) また藤袴(ふぢはかま) 朝貌(あさがほ)の花」(万葉集・巻八 1538)
こちらを春の七草に似せて
「はぎききょう、 くずおみなえしふじばかま、 おばななでしこ、 これぞ秋の七草」とシンプルに覚えてみてはいかがでしょうか。
語呂合わせで
・「お好きな服は?」
記憶に残りやすい語呂合わせの一例です。これは各草花の頭文字を取って構成されています。
お…女郎花の「お」
す…すすき(尾花)の「す」
き…桔梗の「き」
な…撫子の「な」
ふ…藤袴の「ふ」
く…葛の「く」
は…萩の「は」
「尾花」を「ススキ」として覚えておくことが必要ですが、あとは頭の文字をつなげると「おすきなふくは」になります。
・「ハスキーなおふくろ」
上記「お好きな服は?」のアレンジ版です。
は…萩の「は」
す…すすき(尾花)の「す」
きー…桔梗の「き」
な…撫子の「な」
お…女郎花の「お」
ふ…藤袴の「ふ」
く…葛の「く」
頭の文字をつなげると「はすきなおふく(ろ)」「ハスキーなおふくろ」で覚えます。
まとめ

かつて歌に詠まれた秋の七草は、長い年月を経ても変わらず多くの人々に愛され続けています。
ハギ、オバナ(ススキ)、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、アサガオ(キキョウ)
秋を代表する草花の控えめな美しさや風情のある佇まいを観賞すると、深まりゆく秋という季節感を象徴するような情景に心が穏やかになり、あるいは心を動かされて、詩歌や文学が生まれてきたともいえるのではないでしょうか。
秋の七草を覚え、近辺を探してみるなどしてみると、目に映る秋の景色も変わって、より豊かな楽しみが増えるかもしれませんね。


