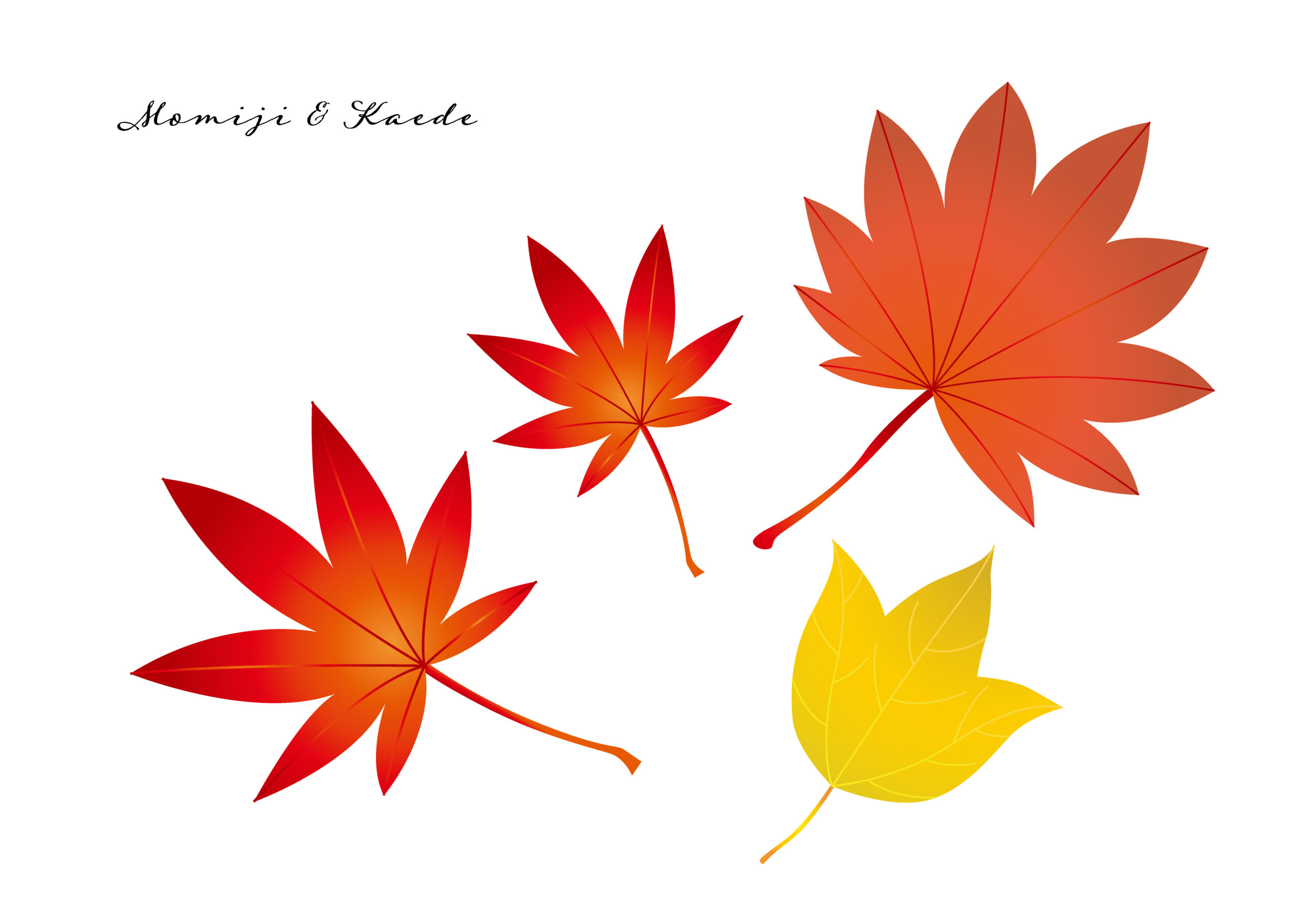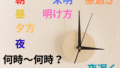紅葉(こうよう)の季節、赤く色づいたその木は、「もみじ」?「かえで」?
一見似ている両者ですが、共通する部分と異なる部分があります。
それぞれの呼び名の由来と、葉形の特徴や日本では紅葉の有無による区別など、違いや楽しみ方について調べてみました。
「もみじ」と「かえで」どこが違う?

紅葉(こうよう)の季節になるとよく耳にする「もみじ」と「かえで」ですが、これらの言葉は童謡「紅葉(もみじ)」において両方とも出てくるところからも、違うものだろうと感じている方は多いのではないでしょうか。
「もみじ」は通常「紅葉」と書き、「こうよう」とも読まれますが、この記事では紛らわしさを避けるため「もみじ」と表記します。
同じく、「楓」もひらがなで「かえで」と表記します。
同じカエデ属で色づく方が「もみじ」
実は、「もみじ」と「かえで」は植物の分類学上、同一の植物グループに属しており、具体的には、ムクロジ科(旧カエデ科)のカエデ属に分類されています。
分類学的には「かえで」という範疇に「もみじ」が含まれる形です。
英語では「もみじ」は「Japanese maple」と表記され、「maple」はカエデ属を指すことから、サトウカエデから採れるメープルシロップの「maple」も、同じく「かえで」を意味するものです。
日本特有の文化では、「かえで」の中でも特に秋に色づくものを「もみじ」と称し、区別しています。
また園芸や盆栽では、葉の形状や色に基づいてこれらを使い分けることもあります。
次に、それぞれの名前の由来を紐解いてみましょう。
「もみじ」の名前の由来
「もみじ」という言葉は、「揉む(もむ)」という動詞に由来します。
平安時代には紅花(べにばな)と呼ばれる植物を使った染色が行われていました。この紅花を水中で揉むことにより色が抽出され、鮮やかな紅色が布に移ります。
この染められた布を「もみ」と称し、そこから草木が紅く色づく様子を「もみつ(紅葉つ)」、「もみち」と表現するようになりました。
「かえで」の名前の由来
「かえで」という名前は、カエデの葉がカエルの手に似ていることから「蛙手(かへるて)」と呼ばれ、やがて「かえで」となったと考えられています。
この表現も、万葉集にはすでに登場しているそうです。
「もみじ」「かえで」いづれの名前の由来からも、かつての日本人がいかに自然と近しい関係にあってよく観察していたからこそ、独自の表現で美しさを表現してきた、という歴史を垣間見ることができるのではないでしょうか。
園芸や盆栽の「もみじ」と「かえで」の区別

日本の園芸分野では、葉の形状に基づいて「もみじ」と「かえで」の名で植物を分類しています。
具体的には、葉に深い切れ込みが多くあるものを「もみじ」と呼び、浅くて切れ込みの少ないものを「かえで」としています。
「もみじ」の特徴
- イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジなどがあります
- これらは手のひらより小さい葉に深い切れ込みが5つ以上あり、非常に繊細な形状をしています
- イロハモミジは紅葉(こうよう)するため「もみじ」の代表例であり、赤ちゃんの手のことを「もみじのような」と例えられるほど親しみやすい形状をしています
「かえで」の特徴
- ウカエデ、イタヤカエデ、ハウチワカエデなどがあります
- 比較的大きな葉に浅い切れ込みがあり、トウカエデなどは3つの切れ込み、ハウチワカエデは9~11の切れ込みでがありうちわのような大きさと、サイズも含め多様な形状をしています
盆栽の分野においても、同様の特徴に基づき「もみじ」と「かえで」が用いられます。
イロハモミジなど葉の切れ込みが5つ以上で紅く色づくものは「もみじ」とされ、その他のカエデ属の植物は「かえで」として扱われています。
両者の違いには多くの例外もありますが、一般的な傾向として以下の表のように整理できます。
| 項目 | もみじ | かえで |
| 葉の切れ込み | 深い(5つ以上) | 浅い(3~11程度) |
| 葉の大きさ | 小さめ(赤ちゃんの手ほど) | 大きめ(団扇のような形も) |
| 色づきの傾向 | 秋に鮮やかに赤・橙に染まりやすい | 黄色~黄緑に色づく種類が多い |
| 代表的品種 | イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジ | トウカエデ、ハウチワカエデ、イタヤカエデ |
| 文化的表現 | 「もみじの手」と子どもの手に例えられる | カナダ国旗のシンボルとして知られる |
あくまでも目安として、紅葉狩りや庭園散策の参考になさってみてくださいね。
また、カナダ国旗は「かえで」として有名ですが、日本以外の国ではあまり「かえで」と「もみじ」を区別せず「かえで」が一般的だそうです。
暮らしの中で楽しむ「もみじ」と「かえで」

紅葉の違いを知っておくことで、日常に新たな発見や楽しみも増えるのではないでしょうか。
例えば:
・紅葉狩りでの楽しみ方
公園や寺社庭園では、同じ場所に「もみじ」と「かえで」が植えられていることも少なくありません。切れ込みや葉の大きさを比べて眺めると、「紅葉狩り」に「観察する楽しみ」が加わります。
最近は、写真に撮るだけで草木の名称を知ることができるアプリやスマホ機能がありますので、ご家族でクイズにすることも可能ではないでしょうか。
・暮らしに根付いた表現を体感
赤ちゃんの手を「もみじのよう」とたとえるように、葉の形は昔から生活に溶け込んできました。散歩の途中でお子さん手と、本物のもみじの落ち葉を当てて比べてみるのも楽しいですよね。
・庭木や盆栽として
鮮やかな紅葉を楽しみたいなら「もみじ」系を、緑で陰を作る丈夫な木として植えたいなら「かえで」系を、と用途によって選んでみてはいかがでしょうか。
よくある質問(Q&A)4つ
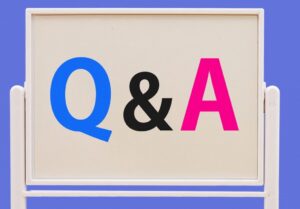
1.すべての「かえで」が紅葉するのですか?
A. 必ずしも赤くはなりません。黄色やオレンジに変わる種類も多く、なかには色の変化が目立たないものもあります。
2.海外では「もみじ」と「かえで」を区別するの?
A. 日本ほど細かくは区別されず、英語ではいずれも「maple」と総称されます。カナダ国旗の葉も、特定の種ではなく「かえで全般」を象徴しています。
3.春に「もみじ」が紅葉することがあるのはなぜ?
A. 春の新芽はまだ葉緑素が少なく、赤いアントシアニン色素が目立つため、一時的に紅葉して見えることがあります。これは「春紅葉(はるもみじ)」とも呼ばれ、秋の紅葉とは異なる自然現象です。
※春紅葉は「個体差」もありますが、日当たりがよく寒暖差のある場所や、アントシアニンを出しやすい品種では、特に鮮やかに生じることがある現象です。
4.庭に植えるなら「もみじ」と「かえで」どちらがおすすめ?
A. 鮮やかな秋の彩りを重視するなら「イロハモミジ」などのもみじが人気です。丈夫さや成長の早さを求めるなら「イタヤカエデ」や「ハウチワカエデ」なども適していますよ。
まとめ

「もみじ」と「かえで」は、植物の分類学上では同じカエデ属に属しており、「かえで」が広義のカテゴリーで、「もみじ」はその中の一種として位置付けられています。
日本では一般的に、特に紅葉する特性を持つ木々を「もみじ」として認識されています。
「もみじ」の名は、動詞「揉む(もむ)」からきており、色付く様子が何かを揉むように変化することを表すところから名付けられました。一方、「かえで」の名は、その葉の形がカエルの手に似ていることから名付けられました。
この「もみじ」を含むカエデ属の木々は、日本の紅葉(こうよう)を代表する象徴といっても良いものであり、「もみじ」と「かえで」どちらも秋の風景に欠かせない存在です。
植物学的には同じ仲間でありながら、いにしえの日本人の独自の感性や表現によって、名前を区別して呼んできた両者の違いを知った上で、紅葉狩りの季節にこれらの鮮やかな紅葉(こうよう)を眺めるというのも、ひときわ感じ入ることができて、楽しいのではないでしょうか。
さいごに、園芸や盆栽における区別について、両者の違いには多くの例外もありますが、一般的な傾向として整理した表を再掲いたします。
| 項目 | もみじ | かえで |
| 葉の切れ込み | 深い(5つ以上) | 浅い(3~11程度) |
| 葉の大きさ | 小さめ(赤ちゃんの手ほど) | 大きめ(団扇のような形も) |
| 色づきの傾向 | 秋に鮮やかに赤・橙に染まりやすい | 黄色~黄緑に色づく種類が多い |
| 代表的品種 | イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジ | トウカエデ、ハウチワカエデ、イタヤカエデ |
| 文化的表現 | 「もみじの手」と子どもの手に例えられる | カナダ国旗のシンボルとして知られる |
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。