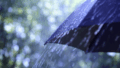中秋の名月「十五夜」の約1か月後に、再び月を愛でる風習「十三夜」をご存じでしょうか?
2025年の十五夜は10月6日(月)、十三夜は11月2日(日)、十日夜は11月29日(土)です。
十三夜は満月より少し欠けた「後の月」の趣を楽しみ、栗や豆をお供えして秋の実りに感謝するお月見です。
さらに、由来の説・別名・お供え物や十五夜との違いを整理し、月見団子の作り方や供え方、ご家族での楽しみ方のヒントについてもご案内しております。どうぞご覧ください。
今年2025年の「十三夜」お月見の日程
- 十五夜(中秋の名月)
2025年は 10月6日(月) です
(かつての暦では 8月15日 に行われていました) - 十三夜
2025年は 11月2日(日) です
(かつての暦では 9月13日 に行われていました)
なお、2025年は中秋の名月(10月6日)と天文学的な満月(10月7日 12:48頃)が1日ずれたため、十五夜の夜はわずかに欠けた月、翌日には満月と、異なる表情を楽しむこともできます。
※詳細は、2025年十五夜は満月?「中秋の名月」の呼び名とお月見の由来をご覧ください。
十三夜のお月見について

十三夜の月とは
「十三夜」とは、月の満ち欠けを基準にした呼び方で、月齢13日目ごろに見える月を指します。
満月の直前で、丸さを帯びながらも左側がわずかに欠けているのが特徴で、肉眼では満月とあまり変わらないという人もいるほどですが、そのほんの少し満ちきらない姿に趣を見いだし、日本人は古くから「未完成の美」として愛してきました。
また、かつての暦では9月13日の夜がこの月齢13日目にあたり、特別に「十三夜」としてお月見が行われてきました。
十三夜お月見の由来と感性

十三夜は、日本で育まれた観月の風習とされています。
平安時代、延喜十九年(919年)に寛平法皇(宇多天皇)が十三夜の月を称賛し「今夜名月無双」と述べられたという記録が残っています。
『躬恒集(みつねしゅう)』には、これを受けて醍醐天皇が父である先帝のために観月の宴を開いたとの逸話も記され、宮中の雅やかな行事がやがて庶民にも広がり、収穫の恵みと結びつきました。
この時期は十五夜の頃よりも天候が安定しやすく、昔から「十三夜に曇り無し」ともいわれ、月見に適した時季と考えられてきました。
また十三夜は、十五夜に続く「後の月」として、そのわずかに欠けた姿に趣を見いだしてきたという文化的背景も影響しているようです。
『徒然草』137段の「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」という一節にもあるように、月の満ち欠けの過程や完全ではない姿に、時をいとおしむ余白のような趣を感じ取るのが日本人の感性であったということではないでしょうか。
別名やお月見の意味
十三夜にはさまざまな別名が存在し、それぞれが季節の恵みや生活と深く結びついています。
収穫後の時期にあたるため、実りに感謝する意味合いが強いのが特徴です。
収穫への感謝
稲の収穫期にあたることから、秋の実りに感謝する日とされてきました。供え物を月にささげるのは、自然の恵みをたたえ、これまでの収穫を振り返る風習であったようです。
地域によっては、稲刈りを終えた後に収穫物を供え、村人が集まって宴を催したという伝承も残されており、共同体としての結びつきを深める役割も果たしていました。
後の月
十五夜の後にやってくるため、「後(のち)の月」とも呼ばれています。
華やかな十五夜に対して、十三夜はしっとりと余韻を味わう時間とされ、その静けさも魅力のひとつです。
栗名月・豆名月

この時期に旬を迎える栗や豆(大豆)にちなんで、「栗名月」「豆名月」と呼ばれています。
収穫された作物を月に供えることで、自然と人とのつながりを感じ取り、感謝の気持ちを示す意味が込められてきたといわれています。
小麦の名月
一部地域では、十三夜を「小麦の名月」と呼ぶこともあります。
十三夜の天候によって翌年の小麦の作柄を占ったという伝承が残り、農耕と生活の結びつきを示す呼び名となっています。
お供え物

十三夜では月見団子に加え、「栗名月」「豆名月」と呼ばれる由来にもなった旬の栗や豆(枝豆・大豆)を供えるのが特徴です。
飾りにはススキや秋の七草のほか、稲の穂を飾る地域もあります(稲穂が手に入らない場合の代わりとして、ススキが用いられてきました)。
お団子の数には地域差がありますが、十三夜は13個とする例がよく知られています(十五夜のお団子は15個とする傾向)。また、必ずしも数を固定せず、奇数であればよいとする地域もあり、奇数を尊ぶ考え方が反映される形なのでしょう。
さらに地域によっては、収穫したばかりの栗ご飯や枝豆、柿や梨などの秋の果物を供えることもあり、季節感あふれる食卓を通じて月を讃える風習が伝わってきました。
こうした供え物は単なる儀礼にとどまらず、家族や近隣が集い、収穫を共に喜ぶ時間をつくり出していたのです。
十五夜との違いや関連

日程・月齢による見え方・意味・別名・お供え物の違い一覧
十五夜と十三夜は、時期や意味合いが異なり、対になる行事として伝えられてきました。以下の表として整理いたします。
| 項目 | 十五夜 | 十三夜 |
| 時期(かつての暦) | 8月15日 | 9月13日 |
| 2025年の日程 | 10月6日(月) | 11月2日(日) |
| 月齢・見え方 | 月齢15夜ごろ、満月または満月に近い月 | 月齢13夜ごろ、満月直前でわずかに欠けた月 |
| 行事の意味 | 稲の実りを迎える前に豊作を祈願 | 収穫を終えた後に感謝を捧げる |
| 別名 | 芋名月など | 栗名月・豆名月・後の月 |
| 主なお供え物 | 里芋、月見団子、ススキ | 栗・豆、月見団子、ススキ、秋の果物 |
このように、十五夜と十三夜は時期も意味も異なりますが、どちらも秋の農耕と深く結びつき、月を通じて自然への祈りや感謝を表す大切な行事とされてきたことが伺えるのではないでしょうか。
※十五夜・十三夜どちらにも月見団子とススキを供えるのが一般的です。
二夜 (ふたよ) の月・片月見
十五夜と十三夜の両方お月見することを「二夜ふたよの月」といい、縁起がよいとされてきました。
片方だけを祝うことは「片月見」と呼ばれ、昔はあまり好まれませんでした。
十日夜を含めた三月見(さんつきみ)とは
お月見三行事として、十五夜と十三夜に十日夜(とおかんや)を加え、「三月見(さんつきみ)」と呼ばれることもあります。
十日夜はかつての暦の10月10日に行われる収穫祭で、2025年は11月29日(土)にあたります。
東日本を中心に広がった行事で、稲刈りを終え、田の神さまに感謝するとともに、来年の豊穣を祈願する日ともいわれています。
地域によっては「刈上げ十日」「かかしあげ」などの呼び名があり、西日本では同時期の亥の子(いのこ)行事に相当します。
子どもたちが藁や石に縄を付けて家々を回り、「亥の子餅」を分けてもらうなど、土地ごとの風習が伝えられています。
この日もお月見してみてはいかがでしょうか?
十三夜のお月見を楽しむ過ごし方

家族で楽しめるアイデア
十三夜は十五夜に比べると知名度はやや低いですが、家庭でゆったりと楽しむにはぴったりの行事です。
ベランダや庭先で月を眺めながらお茶を楽しんだり、子どもと一緒に月の形を観察してスケッチをしてみたりするのも、よい思い出になります。
星座や月の模様を一緒に探すのも、楽しい時間となるのではないでしょうか。
月見団子やお供え物の用意
お月見するなら、お供え物やお供え台も準備して、この季節ならではの風情も感じてみませんか?
白玉粉と絹ごし豆腐で作る月見団子
固くなりにくい月見団子の作り方をご紹介します。
- 白玉粉100gに対して、絹ごし豆腐100gをつぶしながら加えてまとめ、直径2〜3cmに丸めて中央を軽くくぼませて成形します。
- 熱湯でゆでて浮いたらさらに1〜2分、冷水に取って水気を切り、きな粉・粒あん・みたらしなど好みで仕上げます。
供える際は、各地域やご家庭の風習に従い、はっきりよくわからない場合には、十三夜は13個、十五夜は15個を目安にするとよいでしょう。
お供え物を飾る場所
- 月がよく見える方角に置くのが基本です
一般には縁側や庭先、ベランダなど、空を眺められる場所に供えます - リビングや屋内で飾る場合は、窓辺や窓側・床の間に設け、窓から月が見える位置に向けて並べましょう
月見台と代わりになるもの
- 正式には「月見台(つきみだい)」と呼ばれる小さな机や三方(さんぽう)に団子や作物を並べます
- 専用の月見台がない場合は、牛乳パックを10センチほどの高さでカットしてお盆や皿をのせるか、白い布や半紙を敷いたお盆や折り畳みの小机などで代用できます
- 高さを少し出すことで、「月にささげる」雰囲気が出るため、座卓やちゃぶ台でも布を掛ければ立派なお供え台になります
配置の工夫
- 月見団子を中央に並べ、その周囲に栗・枝豆・柿・梨など旬の作物を置くのが一般的です
- ススキや秋草を添える場合は、花瓶や器に入れてお団子の横に飾ります
十三夜におすすめの食べ物

十三夜にちなんだ食べ物として、栗ご飯や枝豆のほか、卵を月に見立てた月見うどんや月見そばは手軽で親しみやすく、少し肌寒さを感じる夜のお食事におすすめです。
さらに、現代風の楽しみ方としては、秋限定の「月見バーガー」やうさぎ・月モチーフの和菓子・洋菓子の「月見スイーツ」なども人気がありますよね。
伝統的なお供え物とともに、季節商品を取り入れて食卓をにぎやかにすることで、世代を問わず楽しめるでしょう。
まとめ

十三夜のお月見は、十五夜に続いて秋の月を愛でる日本独自の行事です。
かつての暦では9月13日にあたり、十五夜(10月6日)からおよそ1か月後に訪れ、稲刈りを終えた収穫の感謝を込めて行われてきました。※2025年の十三夜は11月2日(日)にあたります。
由来には、平安時代の宇多天皇や醍醐天皇の観月の逸話が残り、「十三夜に曇り無し」といわれるほど月見にふさわしい時季とされてきました。
別名の「栗名月」「豆名月」「後の月」「小麦の名月」などは、季節の恵みや農耕と深く結びついています。
お供えには月見団子に加え、栗や豆、柿や梨などの秋の果物を供えるのが一般的です。月を見ながら栗ご飯や枝豆をいただいたり、現代風に月見うどんや季節限定スイーツを楽しんだりするのもおすすめです。
十五夜と十三夜の違いより抜粋
| 項目 | 十五夜 | 十三夜 |
| かつての暦の日程 | 8月15日 | 9月13日 |
| 月齢・見え方 | 月齢15夜ごろ、満月または満月に近い月 | 月齢13夜ごろ、満月直前でわずかに欠けた月 |
| 意味 | 豊作を祈願 | 収穫に感謝 |
| 主なお供え物 | 里芋、団子、ススキ | 栗・豆、団子、秋の果物、ススキ |
2025年のお月見三行事(三月見)の日程
- 十五夜(中秋の名月):10月6日(月)
- 十三夜:11月2日(日)
- 十日夜:11月29日(土)
今年はぜひ、十三夜の夜空も見上げながら、古くから続く行事の意味と秋の実りとともに、お月さまと出会ってみませんか。